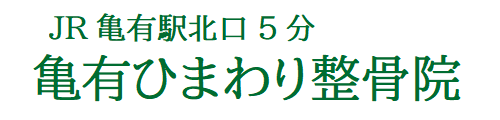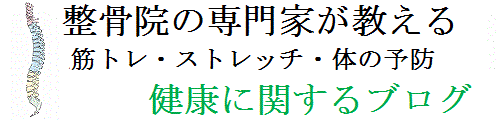亀有で交通事故治療をお探しの方|整骨院でも交通事故治療がうけられます

この記事を読むのに必要な時間は約 18 分です。
亀有で交通事故治療をお探しの方|整骨院でも交通事故治療がうけられます
交通事故での対処方法
もし交通事故の被害にあってしまったら?
そんな交通事故にあったとき、どうすればいいのか?
今回最低限のことは、事前に知っておいた方がいい、交通事故を起こしてしまったときの対処法をご紹介します。
<事故にあった時の手順>
交通事故の被害にあってしまったら?
車の場合、動けるようであれば、安全な場所へ車を移動させます。
1)110番、警察へ連絡する
加害者と被害者両者からの届け出を提出します。
2)相手方(加害者)の氏名、住所と電話番号(連絡先)を書いたメモをもらっておきます。(警察官からその場でもらえます。)
警察を呼んで、現場検証を行うと下記情報等は後で確認できます。
現場で確認できる体の状態であれば、相手方に聞いておきましょう。
・車の登録ナンバー
・自賠責保険
・自動車損害保険の会社名
・証明書番号
・相手方の勤務先や雇主の住所、連絡先、氏名
3)目撃者の証言等があれば確保しておく
万が一裁判になった場合、相手側の黙秘権を覆す有力な証拠となるので、もし目撃者の協力が得られれば、証言をメモしておきましょう。
その際に氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
4)現場の記録
事故後、日が経つと当時の記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後に、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことです。
5)自分の加入している自動車損害保険会社(任意加入している保険会社)へ連絡する
保険会社へ連絡をして、事故車を移動させます。自力走行できない場合は、レッカーを依頼してください。保険会社の「故対応サービス拠点」が遠い場合は、提携する修理工場やロードサービスがあるか、自分の任意保険会社に確認してください。
6)病院にて医師の診断を受ける
交通事故の治療には医師の診断が必要です。
自分の任意保険会社へ連絡をして、病院で診断書を書いてもらいます。
一定期間は通院をします。
被害者となった場合、相手から「示談にしましょう」とある程度の金額を提示される場合があります。この時点で念書やサインなどをしてしまうと、後々保険会社が対応できないことも。当人同士の示談はできるだけ避けるべきです。
事故発生時に救急搬送されるなどして、相手の連絡先などの情報を全く確認していない場合は、「事故証明書」を警察から後日発行してもらうと、加害者側の氏名・住所なども記載されています。
7)警察署へ行き、事故証明のため、事故当時の事情聴取を受けます。
実況見分できちんと自分の意見を主張します。
実況見分調書は、一度作成されると、後で直すことができません。
少しでも違うと思ったら、絶対に自分の意見を主張し、ゆずらないことが大切です。
交通事故で被害者が亡くなり、目撃者がいない場合、事故の状況を証言できるのは加害者だけになります。
証拠を集めるのに被害者ご家族の努力によって、加害者に有利な裁判が覆ったというケースもありますから、可能なかぎり証拠を集めておきましょう。
また、示談交渉に入った時に過失を認めなくなるケースもありますから、現場の目撃者がいるのであれば、その方の名前や連絡先を控えておくとよいでしょう。
■交通事故治療でのかかり方、注意点(被害者)
1、医療機関への通院
治療間隔を空けてしまうと、治療の必要性がないものと判断されるケースもあるために、治療はできるだけしっかり通院することが大切です。
事故後、痛みがなくても、数日してから身体のどこかに痛みがでてきたりすることがあります。
期間があまり経過してから、交通事故が原因で痛くなったと症状を訴えても、交通事故との因果関係を立証することが困難になります。
治療は、整形外科と整骨院での治療が可能です。
整形外科には、最低月1回の受診が必要です。
いずれ示談の時に診断書を発行するときに必要となります。
また、症状固定といって、症状がこれ以上行っても進展がない場合には後遺症障害の認定を受けるために診断書が必要になります。
そのため整形外科で医師の診察を受けていないと、この認定を受けられなくなります。
このようなことから整形外科には月1回は診察を受けておくことが必要です。
治療は、整形外科との併用にて、整骨院(接骨院)での治療及びリハビリが可能です。
むちうちなどによる頚椎捻挫などは治療開始後、早いと3ヶ月、概ね半年くらいで示談交渉の話が損害保険会社の担当者から連絡があります。
骨折などよほど重症とみられるけがではないと長期の治療は、損害保険会社があまり認めてはくれません。
こういった例からも言えるように、治療期間内もおおよその目安をしっかり確認して治療を進めていくことです。
2、無理な治療は控える
損害賠償では、必要かつ相当な治療費等や賠償金額しか認められないのが基本です。
治療を受けるにあたっての交通費や駐車代などの領収書は、示談の際、損害賠償の必要書類提出で必要になりますので、捨てずに保存しておきましょう。
3、示談は弁護士に相談する
示談の交渉は、弁護士に相談してみましょう。
示談をしてしまうと後で覆すことができません。
損害保険での特約で「弁護士特約」に加入していると、示談交渉などをワンストップサービスで行ってもらえます。
弁護士特約に加入している方は、この特約を利用した方が良いと思います。
特約を利用しても、今掛けている保険の等級に影響はありません。
■加害者になってしまったら?
被害者も加害者も手順は概ね一緒です。
安全な路肩などにケガ人を移動します。
事故を起こした場合は、人身事故・物損事故に関わらず必ず警察に報告する義務があります。
事故現場と、事故の状況、負傷者のあるなし等を伝えます。
ケガ人などがいる場合は、救急車を要請します。
警察に「交通事故証明書」を発行してもらわないと、修理等の保険金も出ませんし、相手がある場合は後日の示談交渉にも支障が生じます。
自分が加害者である場合は、保険契約上、保険会社への通知義務があります。
その際には「証券番号」が必要です。
■加害者に発生する3つの責任
人身事故を起こした加害者には、次の3つの責任が個別に生じます。
刑事事件
刑事責任とは、加害者が「罰金刑」、「懲役刑」、「禁錮刑」などの刑罰に処せられることです。
人身事故を起こした罪、事故を起こしたときに酒酔い運転をしていた罪、ひき逃げをした罪などがあります。
民事責任
民事責任とは、被害者に与えた損害を賠償する責任です。
これには、ケガの治療費、ケガをしなければ得られたと見込まれる収入、精神的な苦痛に対する慰謝料などが含まれます。
行政責任
行政責任とは、加害者が免許取り消しや免許停止などの行政処分を受けることです。
自賠責保険
必ず加入しておかなければならない強制保険です。
この保険の役割は「人身損害」のみ。
運転中に事故を起こし相手に怪我を負わせた場合、相手の治療費は補償されますが、相手の車の修理代や自分の車の修理代、自分の怪我の治療費も補償されません。
任意保険
入るプランによってはかなり厚い補償が受けられます。
相手への治療費(人身事故)、相手の車の修理代(物損事故)、自分の車の修理代(車両保険)、自分の治療費(自損事故)。
限度額も自賠責に比べるとかなり高額です。
相手との示談交渉も代行してくれますし、仮に示談で治まらず訴訟等に発展してしまった場合でも弁護士等を立ててもらえ、裁判にかかる費用も保険会社が負担してくれます。
※自分が入るプランによって変わってきます。
万が一に備えて、万全な保険に加入しておく事をオススメします。
■相手が自賠責保険に加入していないときは?
自賠責保険は強制加入であり、これに加入していない自動車を運転してはならない、と法律で定められているものです。
万が一、相手方が強制加入であるはずの自賠責保険に加入していない場合は、「政府保障事業」という制度を利用するとよいでしょう。
無保険者が事故を起こした場合や加害者がどこの誰か分からない場合に、自賠責保険と同額の補償をしてくれる制度です。
また、被害者自身や同居の親族などの任意保険に「無保険者傷害特約」があれば、その保険から損害賠償相当額が支払われる場合がありますので確認することが必要です。
■交通事故損害賠償の種類
交通事故の損害賠償には、大きく分けて人身損害と物件損害があります。
人身損害
人身損害は人の体に生じた損害のことで、財産上の損害と精神的苦痛(慰謝料)に分類されます。
財産上の損害は、さらに積極損害と消極損害に分類されます。
積極損害
被害者が交通事故により支出を余儀なくされる費用のこと。
治療関係費(応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、看護料、療養中の文書料等)、器具代、付添費、将来介護費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、交通費、弁護士費用、損害賠償請求関係費用等。
消極損害
交通事故がなければ被害者が得ていたはずの経済的利益(収入)のこと。
休業損害:交通事故による傷害のために仕事を休んだことで、得られるはずの収入を得られないことに対する損害
逸失利益:交通事故がなければ将来的に得られていたであろう利益
慰謝料
交通事故に遭い、精神的な苦痛を強いられた(精神的損害)ことに対する損害賠償のこと。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
物件損害
修理費、買替費用、代車代、事故歴がつくことによる評価損(格落ち)など。
■賠償額
通常、最も重い後遺症が残った場合、自宅のリフォーム費や介護費なども含まれますから、賠償額は1億円を超えるのが普通です。
自賠責保険で支払われる限度額は4000万円です。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
自賠責保険における慰謝料の額
傷害による損害
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円。
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級) 。
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円。
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
支払対象にならないケース
■被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
■被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
■追突した側が被害車両の場合
■損害賠償 請求権の時効
加害者に対して
保険会社に対して
保険会社に対して
自賠責保険の場合、原則として事故から3年、後遺症に関する損害賠償請求権は症状固定から2年で時効になります。
この時効は保険会社に「時効中断承認申請書」を届け出て承認してもらえば中断することができます。
特に注意すべきは後遺症認定を時効がくるまえに保険会社に請求しなければならないという点です。
これを怠ると後遺症等級を認定してもらうことができなくなってしまいます。
■弁護士費用の相場
交通事故における弁護士費用の相場は第二東京弁護士会の報酬会規が参考になります。
厳密に言えばこれは現在は廃止されていますが、基準にはなります。内容は下記のとおりです。
<経済的利益額> <着手金> <報酬金>
300万円以下 8% 16%
300万円超3000万円以下 5% +9万円 10% +18万円
3000万円超3億円以下 3% +69万円 6% +138万円
3億円超場合 2% +369万円 4% +738万円
■示談交渉が成立しない場合
示談交渉は、被害者のケガが完治してから始めます。
示談金の相場とは慰謝料の相場です。
原則として、いったん示談が成立すると、後で示談当時と異なる事実関係が分かっても、示談のやり直しができません。
示談が成立しない場合の次の段階として一般的には調停と訴訟のふたつがあります。
交通事故の損害賠償 示談が成立しない場合の調停と訴訟
調停
調停は裁判所に手伝ってもらい、あくまでも話し合いを元に合意を目指す手段です。
ですから、争点となる賠償金額が高ければ高いほど調停が成立する率は少なくなり、交通事故では多くのケースで調停ではなくもうひとつの手段である訴訟が用いられます。
訴訟
訴訟では、話し合いではなく「判決」によりはっきりとした結論が出ることがわかっています。
交通事故の裁判は複雑な知識・戦略が必要とされますので、可能なら弁護士に頼んだほうがよいでしょう。
最終的には証人尋問に入るわけですが、多くの場合、そのまえに裁判所から和解の勧告が行われます。
なぜかと申しますと、通常のケースでも1年程度かかるのは珍しいことではありません。
また、医学的論争が関わってくる場合などは2-3年かかるケースもあります。
■加害者が自己破産した場合
加害者が任意保険に未加入で、自賠責の賠償金や自己加入損保の不足額を加害者本人に対して請求するとき、場合によって加害者は自己破産という手段を取ることがあります。
その場合、破産法第253条第1項により借金を支払う必要がなくなってしまうため、損害賠償を受け取ることができません。
加害者が事故前に破産手続きを行っていた場合は関係ありません。賠償請求できます。
こういったケースで被害者側が取れる唯一の有効的な手段は、訴訟を起こし、損害賠償請求権の時効を10年まで延期してもらうことです。

<ご質問お問い合わせは下記より>
◆ホームページ◆
https://himawari-seikotsuin.com/
◆院長大須賀に相談してみる
http://www.firstchecker.jp/dx/form/1201/
メルマガでもっと濃い内容をお届けしています。
無料メルマガ興味のある方は下記から。
メルマガは、ひまわり通信「幸せは、まず健康から」という件名で届きます。
http://ws.formzu.net/fgen/S78617244/
無料レポート
▶「日常簡単に出来る肩こり予防体操ストレッチ」
興味のある方は下記から
https://peraichi.com/landing_pages/view/himawari-katakori
▶「日常簡単に出来る腰痛予防体操ストレッチ」
興味のある方は下記から
https://peraichi.com/landing_pages/view/himawari-youtuu
Copyright © 整骨院の専門家が教える健康に関するブログ All rights reserved.